
人がこの世に生まれてから、この世界は一体何なのか?自分とはどういう存在なのか?人生ってどうやって生きて行けばいいのか?…等々、世界観、人間観、人生観などができるまでのプロセスってどんな感じなんだろう。どの段階でどんな影響を受けて構築されていくのだろうか…。
人が生まれてから「この世界とは何か?」「自分とは何者か?」「人生とはどう生きるべきか?」といった世界観・人間観・人生観が形成されるプロセスは、以下のような段階を経て進んでいきます。それぞれの段階で受ける影響によって、個々の価値観が作られていきます。
1. 乳幼児期(0~3歳) 〜【無意識の吸収】〜
🔹主要な影響要因:親・養育者、環境、身体感覚
- 生まれたばかりの赤ちゃんは、世界を「安全か?危険か?」という基本的な感覚で捉える。
- 言語を理解する前に、親や養育者の表情、声のトーン、スキンシップを通じて「自分は愛されている存在なのか?」を感じ取る。
- 身体的な快・不快の感覚(お腹がすいたら泣く→ミルクをもらえる、寒いと感じたら抱っこされる)を通じて、世界との関わり方を無意識に学ぶ。
→ この時期の愛着形成(アタッチメント)が、その後の人生観・人間観に大きな影響を与える。
2. 幼児期(3~6歳) 〜【自己と他者の区別】〜
🔹主要な影響要因:親、家族、遊び、物語、幼稚園・保育園
- 「自分」と「他者」の違いを意識し始める。
- 家族や保育園の先生、友達との関わりを通じて「自分はどんな存在か?」を感じる。
- 物語やアニメ、絵本の影響を受け、善悪の概念や世界のルールを学ぶ。
- 「なぜ?どうして?」と質問が増え、世界の仕組みを理解しようとする。
→ この時期に「自己肯定感」が形成される。愛される経験が少ないと「自分は価値のない存在」と感じることもある。
3. 児童期(6~12歳) 〜【社会のルールを学ぶ】〜
🔹主要な影響要因:学校、先生、友達、遊び、メディア
- 小学校に入ると「ルール」が重要になる(時間を守る、宿題をする、順番を守る)。
- 友達との比較を通じて「自分は何が得意か?」「自分はどんな性格か?」を知る。
- 親の影響がまだ強いが、先生や学校の価値観に影響を受け始める。
- 社会の常識や善悪、道徳観を学び、「こう生きるべき」という考え方が形成される。
→ この時期に「努力すれば報われる」「運が全て」などの人生観の基盤が作られる。
4. 思春期(12~18歳) 〜【アイデンティティの確立】〜
🔹主要な影響要因:友人、メディア、社会、教師、SNS
- 親からの影響よりも「同世代の仲間」の影響が強くなる。
- 反抗期を通じて「自分は何者か?」「なぜ生きるのか?」と深く考える。
- 音楽、映画、SNS、ゲームなどの文化的な要素が世界観の形成に影響を与える。
- 恋愛や友情を通じて「他者との関係性」の価値観が固まる。
→ この時期に「自分らしさ」「自分の生きる意味」を模索するようになる。
5. 青年期(18~30歳) 〜【人生観の方向性が決まる】〜
🔹主要な影響要因:大学、仕事、恋愛、挫折、成功体験
- 親の価値観と自分の価値観のズレに気づき、自分の人生を選択し始める。
- 仕事や社会経験を通じて、社会のリアルな構造を学ぶ。
- 「お金」「自由」「責任」といった現実的なテーマに直面し、人生観を修正していく。
- 挫折や成功体験を経て「努力と運の関係」「人間関係の本質」などを実感する。
→ この時期に「自分の人生はこう生きる」と決める方向性が固まる。
6. 壮年期(30~50歳) 〜【社会との関わりを深める】〜
🔹主要な影響要因:結婚、子育て、仕事、社会的責任
- 結婚や子育てを経験すると、親としての価値観が形成される。
- 仕事の中で成功や挫折を経験し、「人生の優先順位」が変わる。
- 若い頃の理想と現実のギャップに向き合い、「人生とは何か?」を再考する。
- 子供の教育を通じて、自分が受け継いできた価値観を次の世代に伝えようとする。
→ この時期に「人生の目的」や「社会との関わり方」に意識が向かう。
7. 老年期(50歳以降) 〜【人生の意味を振り返る】〜
🔹主要な影響要因:家族、健康、死生観、社会貢献
- 定年退職や子供の独立を経験し、「自分の存在意義」を再評価する。
- 健康や死を意識し始め、「人生の意味」や「来世」「魂」などのスピリチュアルな思考が強まることもある。
- 社会貢献や地域活動に関わる人も増え、人生の最終章として「何を残すか?」を考える。
- 「人生をどう生きたか?」を振り返ることで、満足感を得るか、後悔するかが決まる。
→ この時期に「人生とは、どんなものだったか?」という最終的な人生観が確定する。
まとめ:世界観・人間観・人生観はどのように作られるのか?
- 幼少期の愛着形成(0〜6歳)で「自分の存在価値」や「世界は安全か?」が決まる。
- 思春期の自己探求(12〜18歳)で「自分は何者か?」「人生とは何か?」を模索する。
- 社会経験と挫折・成功体験(18〜50歳)で「人生の目的」「価値観」が形づくられる。
- 老年期の振り返り(50歳以降)で「人生の意味」を再定義する。
結局のところ、「どんな環境で育ち」「どんな人と出会い」「どんな経験をするか」が世界観・人間観・人生観を決定する要因となります。

「自分は何者か?」「何のために生まれてきたんだろう?」「人生の意味は?目的は?」など、自分について、人生の意義や目的について考えるのは、誰もが考えるものなのでしょうか?そんなことは全然考えない人もいるのでしょうか?
「自分は何者か?」「何のために生きるのか?」といった 人生の意義や目的 について考えることは、すべての人が必ず経験するわけではありません。人によって、考える深さや頻度には大きな違いがあります。
① ほぼすべての人が一度は考える
- 幼少期や思春期、人生の転機(挫折・成功・死別など)に直面したとき、多くの人が「なぜ自分は生きているのか?」「人生とは何か?」と考えます。
- 特に 思春期(12~18歳頃) は、自我が確立される時期で、多くの人が「自分とは何か?」を模索します。
- 哲学的思考が強い人 は、成長後も人生の意味を深く考え続ける傾向があります。
② しかし、「人生の意味」をあまり考えない人もいる
一方で、「人生の目的や意義を深く考えない」人もいます。その理由には、以下のようなものがあります。
1. 目の前のことに集中して生きている
- 日々の仕事・家庭・趣味に忙しく、「人生の意味」を考える余裕がない。
- 「とにかく生きることに精一杯」という状況では、哲学的な問いを持たないことも多い。
2. そもそも疑問を持たないタイプ
- 「人生は考えるものではなく、ただ楽しむもの」と自然に受け入れている。
- 物事を深く考えるよりも、直感的・感覚的に生きるタイプの人。
3. 宗教や信念によって既に答えを持っている
- ある特定の宗教や信条を持っている人は、「人生の目的」に対する明確な答えを持っている場合が多い(例:「神が与えた使命を果たすために生きる」「魂の成長のために生きる」)。
- すでに確固たる人生観があるため、改めて深く考えないこともある。
4. 社会や環境によって考えさせられる機会がない
- 家庭や学校で「人生の意味を考える」ような環境がなかった。
- 「生きる意味なんて考えるのは無駄」といった考え方が周囲に強いと、自分もそう思うようになる。
③ 人生の転機で初めて深く考える人もいる
普段は深く考えない人でも、以下のような出来事をきっかけに、「人生の意味とは?」と考え始めることがあります。
- 身近な人の死 → 「死んだらどうなるのか?」「生きるとは何か?」と考える。
- 大きな挫折や失敗 → 「自分は何のために生きているのか?」と問い直す。
- 成功体験や達成感 → 「自分は何のために生まれてきたのか?」を考える。
- 老年期 → 「自分の人生は何だったのか?」と振り返る。
④ まとめ
✔ すべての人が「人生の意味」について一度は考える可能性があるが、深く考え続ける人とそうでない人がいる。
✔ 思春期・人生の転機・哲学的性格の人は考えやすい。
✔ 目の前の生活に集中している人、宗教的な答えを持っている人はあまり考えないこともある。
✔ 大きな出来事(死別・挫折・成功)で考え始めることもある。
つまり、「人生の意味を考えること」は普遍的なテーマではあるものの、「どれだけ深く考えるか」は人それぞれ違う、ということですね。

現代は「考えても答えが出ないことを考えても仕方がない」「そんなことより仕事」「そんなことより楽しいことを…」と考える人が多いように感じます。これは今の時代に限らない現象でしょうか?
「いくら考えても答えが出ないことを考えても仕方がない」と考える人が現代には多いと感じる、というのは確かに一理あります。ですが、これは現代特有の現象なのか、それとも昔からあった考え方なのかを整理すると、次のような視点が見えてきます。
1.「答えのない問い」を考えない傾向は昔からあったのか?
実は、「答えの出ない問いを考えても意味がない」という考え方自体は昔から存在していました。
例えば、古代ギリシャのソクラテスの時代から「哲学的な問い」をめぐる議論はありましたが、それに対して「そんなこと考えても無駄」と言う人は一定数いました。
- 実利的な生き方を重視する人々(商人や職人など)は、「生きるために必要なことを考える方が重要」と捉えていました。
- 宗教的な信仰を持つ人々は、「答えは神が決めるもの」として、あまり深く考えないこともありました。
つまり、「考えても仕方がない」という考え方自体は昔から存在していたと言えます。
2. では、現代は「考えない人」が増えているのか?
(1) 科学と合理主義の影響
現代社会では、科学的・論理的に説明できるものが「正しい答え」だとする風潮が強くなっています。
- 例えば、「なぜ生きるのか?」と考えても、科学的に証明できる答えはない。
- だから「答えの出ないことを考えても無駄」と考える人が増えている。
また、技術の発展によって、実用的で具体的な答えをすぐに得られる環境になっているのも要因です。
- インターネットで検索すれば、大抵の疑問には答えが見つかる。
- しかし、検索しても答えが出ないような哲学的な問いには「考えるだけ時間の無駄」と感じる。
このように、「すぐに答えが出るもの」が良しとされる風潮が、考えることを減らしている可能性があります。
(2) 生活環境の変化
昔は「人生の意味」や「自分の存在意義」について考える時間が比較的多かった。
- 例えば、夜になればやることが少なく、静かな時間の中で考え込む機会があった。
- 自然と向き合う生活をしていると、生命や宇宙について考えることもあった。
一方で、現代はどうか?
- スマホやSNS、娯楽が豊富で、考える時間が減った。
- 忙しく働いている人が多く、深く考える余裕がない。
- AIやインターネットが「答えを提供してくれる」ため、自分で考える習慣が減った。
→ これらの要因が、現代の「深く考えない傾向」を強めている可能性が高い。
(3) 資本主義・消費社会の影響
資本主義社会では、「生きる目的を考えるよりも、消費することに目を向けさせる仕組み」がある。
- 例えば、「人生の意味を考える」よりも、「新しい商品を買えば幸せになれる」という価値観が広まっている。
- 考えることよりも、消費することが重要視される風潮が強まっている。
また、現代のビジネスモデルでは、「人々が深く考えること」よりも、「人々がすぐに満足できること」に重点を置いている。
- 例えば、YouTubeやSNSは「短時間でわかりやすい情報」を提供し、考え込む時間を減らしている。
3. まとめ:「考えない人が増えた」と言えるのか?
✔ 「答えの出ないことを考えても仕方がない」と考える人は、昔から一定数いた。
✔ ただし、現代は「考えなくても済む仕組み」が増えたため、深く考える人が減った可能性がある。
✔ 科学・合理主義の発展、インターネットやSNSの影響、消費社会の仕組みが、深い思索の機会を奪っている。
つまり、「考えない人が増えた」というよりも、「考えなくても生きていける環境が整った」と言えるのではないか と思います。
4. では、「考える人」が増えることはあるのか?
「人生の意味」や「自分の存在意義」を考える人が増えるとしたら、どんな時か?
- 社会や経済が不安定になった時
- 例)戦争や経済危機、パンデミックなどが起こると、人は「生きる意味」を考えるようになる。
- AIが進化しすぎて「人間の役割とは何か?」という問いが重要になる時
- 例)仕事の多くをAIが代替すると、「人間は何のために存在するのか?」と考える人が増えるかもしれない。
- 個人が意識的に「考える時間」を確保するようになった時
- 例)デジタルデトックスや瞑想、哲学カフェなど、「考えること」に価値を置く文化が広がる。
5. 最後に
結局のところ、「人生の意味」を考えるかどうかは 環境と個人の性格の影響 によるところが大きいです。
現代は「考えなくても生きていける社会」になっているため、考える人が減ったように見えるかもしれません。
しかし、どんな時代でも 深く考える人は一定数いる し、「考えることの価値」が見直されるタイミングもあるでしょう。
歴史を振り返ると、「考えなくてもよい時代」が続いた後には、必ず「考える時代」がやってくる ものです。

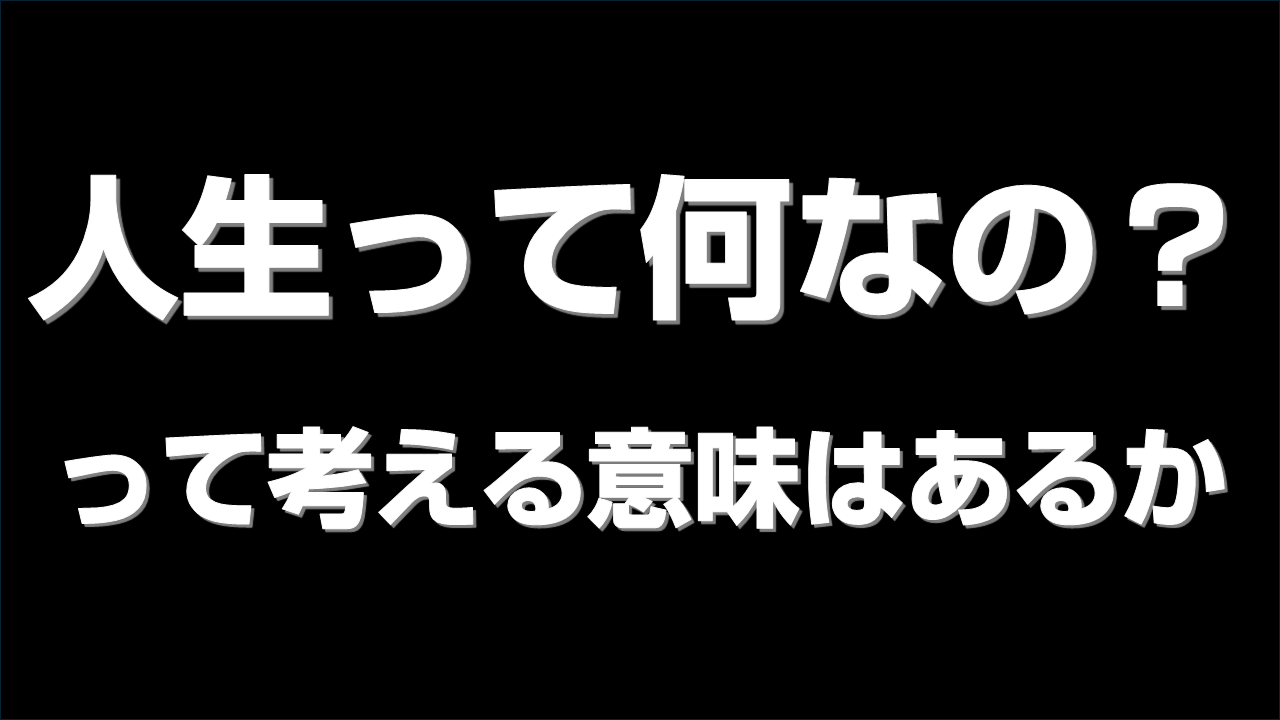
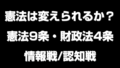

コメント