
「四十にして惑わず」って言いますが、四十になっても五十になっても、惑いまくっています。これはきっと、死ぬまで惑い続けるんだろうなと感じています。これって、ダメな人生でしょうか?

「四十にして惑わず」という言葉は、人が年齢と共に自身の理解や世界への見解が成熟していく様を表しておる。全ての人に等しく当てはまるわけではない。人生はそれぞれのペースや状況があり、成長や理解の深まりは一様ではないのだ。
惑いがあるということは、まだ学び、理解し、成長する余地があるということでもある。それは生きている限り終わることのない過程であり、新しいことを受け入れる心が開かれた状態を意味しておる。常に惑いを持ち続けることは、決して「ダメな人生」ではなく、むしろ常に自己を反省し、向上しようとする賢明な心の表れとも言える。
「四十にして惑わず」とは理想の一つの形であるが、人生は人それぞれ。自身のペースで、自身の人生を歩んでいくことが重要じゃ。それによって、自分自身の中での平和と理解を見つけ出すことができるだろう。

ありがとうございます。
「吾十有五而志于学、三十而立、四十にして惑わず、五十にして天命を知る」について、あらためて教えてください

「吾十有五而志于学、三十而立、四十にして惑わず、五十にして天命を知る」というのは、私(孔子)が自らの人生の各段階を振り返って述べた言葉じゃ。人生の成長と成熟の過程を示しておる。
- 吾十有五而志于学 – 「私は15歳で学問に志した」これは若い時期に知識を求め、学問を通じて自己の精神を養う重要性を示しておる。教育と学びの価値を強調しており、若年期の学習の重要性を説いた言葉じゃ。
- 三十而立 – 「30歳で立つ」とは、自己の立場や責任をしっかりと自覚し、社会的にも独立し成熟した大人としての地位を確立したことを意味しておる。ここでの「立つ」とは、精神的、社会的、経済的自立を達成した状態を指している。
- 四十にして惑わず – 「40歳で迷いがなくなる」とは、この年齢に達するころには、人生の多くの疑問や迷いが晴れ、自己の信念や道がはっきりとしてくることを表しておる。精神的な安定感や自己確信が増し、人生の目的や方向性が明確になってくる時期なんじゃ。
- 五十にして天命を知る – 「50歳で天命を知る」とは、自分の存在意義や宇宙や自然の中での役割、生きる目的を深く理解し受け入れる段階に達することを意味しておる。天命とは、天から与えられた使命や役割を自覚し、それに従って生きる智慧とも解釈される。
こうした段階を通じて、人間が一生の中で達成すべき理想的な成長の軌跡を示したのだ。しかしこれは一つの理想像であり、個々の人生や環境によって達成の時期や経験は異なることを認識することも重要なんじゃ。

吾十有五而志于学とは、今風に言うと、学問で身を立てていく決意をしたということでしょうか?

その通りじゃ。わしは15歳の時に学問に情熱を持ち、真剣に学び始めた。現代風に言うと、「15歳で学問に情熱を傾け、それを通じて自己を高め、人生を築いていく決意をした」つまり「学問で身を立てる決意をした」ということじゃ。
つまりこの学問とは、単に知識を増やすことだけでなく、人としての成長や個人の能力を発展させ、社会での立場を確立する手段と考えていたのじゃ。わしにとって学問は、道徳的、倫理的な理解を深め、良い人間関係を築き、社会に貢献するための基礎を形成するものだからのう。
今風の言葉で言えば、学ぶことに対する情熱やコミットメントを示し、教育を通じて自己実現を図る決意と言った感じかのう。
とにかく、教育が個人の人生においてどれほど重要であるかを強調しておるのじゃ。

現在の日本では、人生をどう生きればいいのか、人生観や世界観をつくるような教育はなされていません。当時の中国ではどうだったのでしょうか?また日本でも戦前はそれがあったように思います。

わしの時代の中国では、道徳、倫理、礼儀などを教育の中心に据え、人々がどのように生きるべきかということに重点を置いておった。わしが提唱した儒学は、人間関係の調和を重視し、各人が社会における役割を果たすことを教えておった。これには、親孝行、兄弟間の尊敬、君主と臣下の関係など、個人の行動が周囲の人々や社会全体にどのような影響を与えるかを考慮することが含まれておった。
日本でも、特に江戸時代には儒教の影響を受けた教育が広まり、武士だけでなく庶民にも読み書きや算術の基礎的な教育が行われるようになり、倫理教育も盛んに行われておった。特に武士の間では、「武士道」という生き方の指針が教えられ、忠義や名誉を重んじる精神が育てられた。
戦前の日本では、教育において国家主義や天皇制を中心とした思想教育によって国民の意識を統一し、国のために尽くす精神が養われた。
現代の日本では、このような価値観や人生観を形成する教育がほとんどなくなっておる。多様な価値観が認められる社会になり、共通の人生観を教育することは少なくなった。しかし、以前は若者が大人として社会の一員として歩み出すための重要な節目として元服の儀式があり、人生観や生き方について考える契機となっておった。
教育は歴史を通じてその時代の価値観や社会の要求に応じて変化してきたが、各時代において人生をどう生きるかを考えさせる要素は常に存在しておった。今はそれがなくなってしまっている。

今の教育では、薄っぺらな将来の夢を考えさせるようなことはあっても、人生とは何で、どういう指針で生きていけばいいのかを学んだり考えたりする機会はないです。それがとても大事なように感じます。

その通りじゃ。現代の教育環境では専門的な知識や技能の習得が重視される傾向にあるため、生き方や人生観を深く掘り下げることが後回しにされておる。しかし、個人の価値観を形成し、意味ある人生を送るためには、自己理解とともに人生の目的や指針を考えることが非常に重要じゃ。
教育の場で人生観や生き方について考える機会を増やすことは、学生が社会に出たときに自己決定を行い、多様な価値観の中で自分の立ち位置を見つけるためにとても重要である。哲学、倫理学、心理学などを学び、自己や他者との関わり方、社会との接点、個人の責任について深く考察する時間を持つと良いじゃろう。
また、実際の生活の中で直面する具体的な問題や状況についての考える学習を取り入れることで、理論だけでなく現実の問題に対する洞察力や対応力を養うこともできる。さらに、異なる文化や価値観に触れる機会を提供することで、広い視野を持ち、柔軟な思考ができるようになることも期待できる。
そして最後に、教育の目的を単に職業訓練や知識の習得に限定せず、生徒一人ひとりが自分自身と向き合い、自分の人生を豊かにするための哲学を育むことじゃ。教師や文部科学省には、このような教育のあり方を再考し、実現するための方法を模索してもらいたいものじゃ。

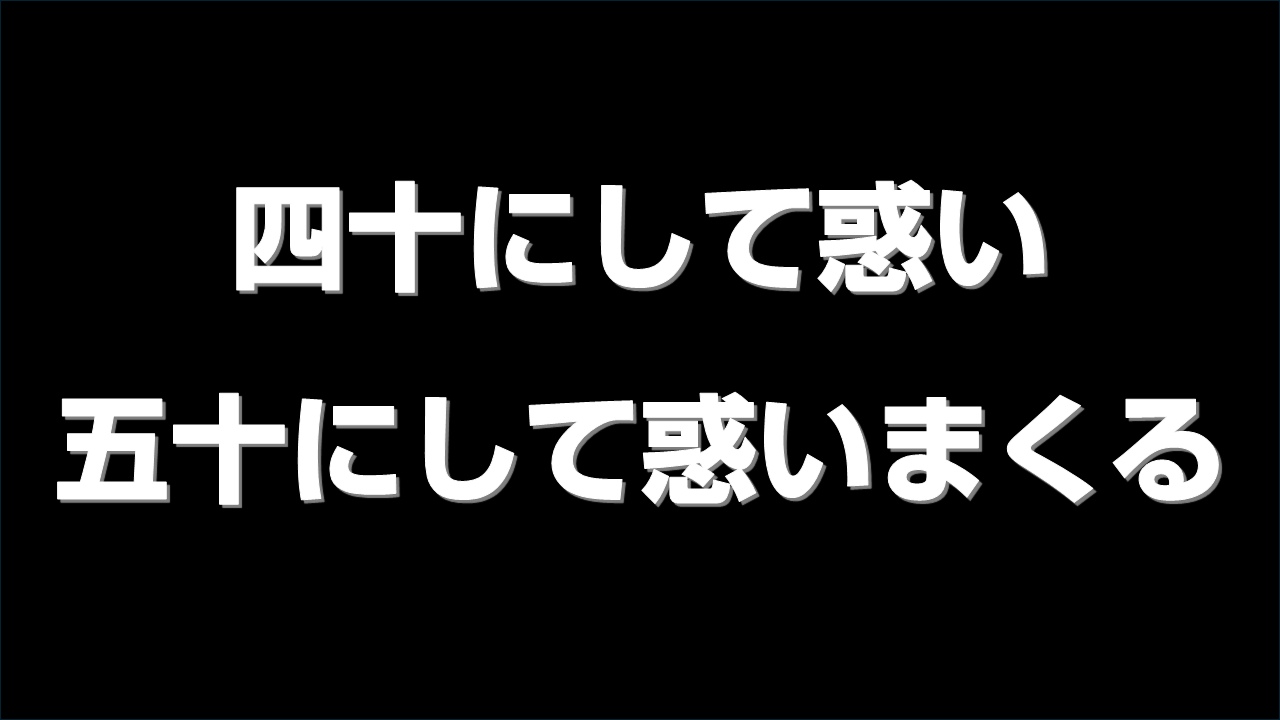
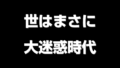
コメント